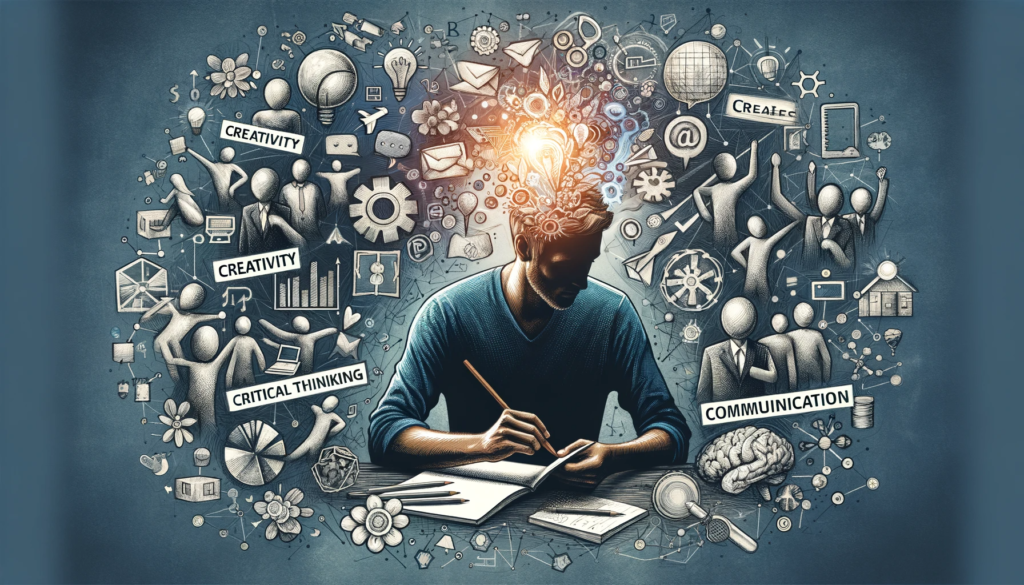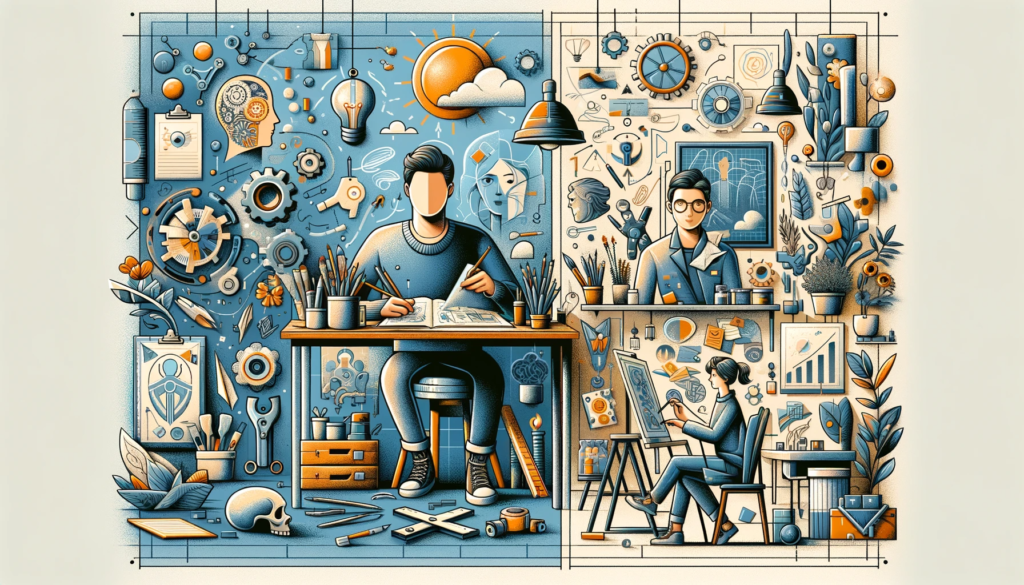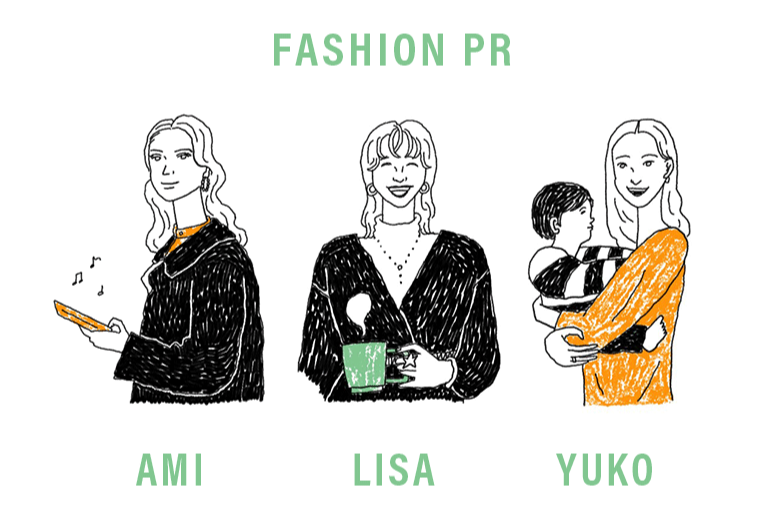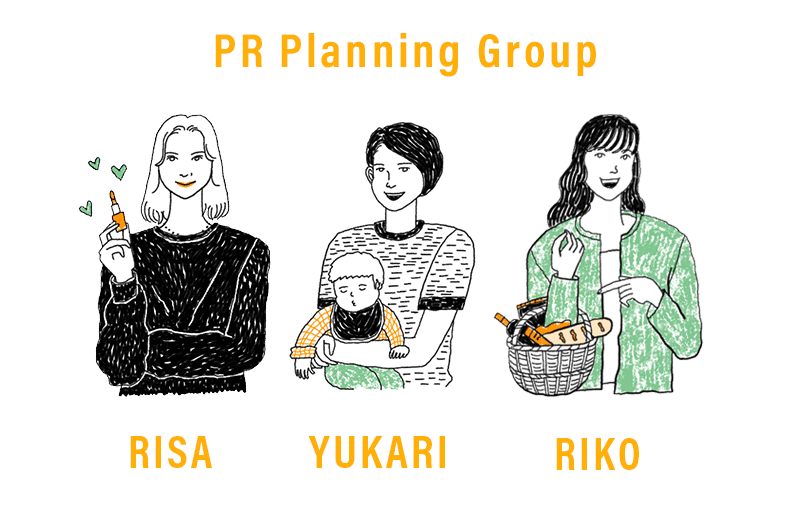オウンドメディアとは、ユーザーの興味を引く有益な情報を発信する役割を担います。オウンドメディアでうまく集客できると、売上向上につながったり、ユーザーからの信頼を強められたりするメリットが期待できます。
しかし「オウンドメディアってどうやって作るの?」「適切な集客方法を知りたい」と考えている方もいるでしょう。よいオウンドメディアの特徴や作り方、構築や運用にかかる費用についてご紹介します。ぜひ参考にしてください。
▼弊社オウンドメディアの事例はこちら
■Vibrram
日本限定のオウンドコンテンツ「Vibram-ism」の立ち上げをサポート
■資生堂プロフェッショナル
サイトトラフィック最大化に向けた支援 /資生堂プロフェッショナル
■ルミアグラス
認知拡大のためのデジタル施策!アイライナーブランド「ルミアグラス」のオウンドコンテンツの制作
良いオウンドメディアの特徴
オウンドメディアの記事は、誰が読んでも理解できる分かりやすい文章で書く必要があります。
取材から得られる一次情報といった内容を盛り込み、独自性を出すのも有効です。よいオウンドメディアの特徴について詳しく紹介していくので、参考にしてください。
オウンドメディアのより詳細な意味や、立ち上げる目的と運用のポイントをこちらの記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
参考記事:オウンドメディアとは?意味や立ち上げる目的・運用のポイントを紹介
誰が読んでも理解できる文章で書かれている
ユーザーフレンドリーなコンテンツを心がけましょう。読者は基本的に、記事を飛ばし読みしたり、流し読みをしたりするのはもちろん、わかりにくい表現で記載されていると離脱する原因となります。
読者が離れてしまわないように、簡単な言葉でわかりやすく書くほか、一目で書かれている内容を理解できるような見出しをつける意識が重要です。
「これ・この」「それ・その」「あの・あれ」「どれ・どの」といったこそあど言葉は、飛ばし読みするときに、どの部分を指しているのか分からなくなりやすいため避けましょう。上記以外には「非常に」「とても」「とくに」など、副詞の多用も避けるようにしてください。
イラストや図表などが使われている
オウンドメディアの記事において、イラストや図表、画像は、読者の印象を決める重要な要素のひとつです。
いくら内容が充実している記事であったとしても、画像やイラストがほとんどなかったり、イメージに合っていなかったり、クオリティの低いものだったりすると、読者が離脱してしまう可能性があります。
文字だけのテキストは、読むのを面倒に感じてしまう可能性があります。テキストだけで説明したものよりも、図表を用いて解説している記事のほうが読者にとって理解しやすいです。
マーカーや文字色を変えて重要な部分が一目で分かる
読者は何が大切なことか、この記事で伝えたいことはどのような点なのか、素早く理解したいと思っています。そのため、マーカーや文字色を変えて、重要な部分を一目で理解できるよう工夫しなければなりません。
また、読者はじっくり文章を読まず、装飾された文章をさっと読む傾向にあります。そういった点もよく理解して、装飾された文字だけでも意味が伝わるように工夫しましょう。
冗長な文章が削られている
冗長表現とは、文章のなかに内容と関係ない表現や単語があり、読みづらくなっている状態を指します。文章に不要な言い回しが含まれていると、一文が長くなり、意図が伝わりにくくなってしまいます。
冗長表現など文章の無駄を省けば、すっきりとわかりやすいテキストに仕上がります。自分で執筆する場合、知らず知らずのうちに冗長表現を用いているケースも多いため、書き上がった記事を音読して確認するとよいでしょう。
使ってしまいがちな冗長表現は、以下のとおりです。
・ 「の」を連続で使っている
・ 二重敬語を使用する
・ 一文のなかに同じ単語を繰り返し用いる
・ 二重否定を使用する
・ 同じ単語を繰り返し用いる
・ 同義語や類語を重複している
また、以下のように、回りくどい言い方はなるべく簡潔な言葉で置き換えるよう、意識しましょう。
・ ~することができる→~できる
・ ~があるものである→~がある
・ ~というものがある→~である
取材や体験談などの一次情報がある
オウンドメディアには、取材や体験談などの一次情報を盛り込みましょう。一次情報を盛り込むと、ほかのメディアと差別化を図れ、情報の信頼度の高さをアピールできるからです。
二次情報は、少なくない複数人が情報を持っている可能性があります。ほかのサイトよりも有益な情報を載せるためには、なるべく一次情報を収集するとよいでしょう。
専門家による監修を受けている
オウンドメディアの運営は、内容の網羅性についても意識していきたいポイントです。読者にとってより有益な情報を届けるためには、専門家など監修者を用意するのも有効です。
記事に専門家ならではの視点を盛り込み、情報の信憑性を高められるよう意識してみましょう。
調査や論文などのデータを活用している
論文のような専門的なコンテンツをはじめ、現場の一次情報が理解できるインタビュー記事、調査などを盛り込むのも有効です。その領域にいる読者からすると、一次情報はとくに知りたい情報でしょう。
とくにニッチな領域のオウンドメディアは、アクセス数が少ない傾向にありますが、情報の希少性が高く、ターゲット層からすると重宝されやすいと考えられます。
調査や論文などのデータを掲載しておくと、競合との差別化も図りやすく、自社の専門性をアピールする材料として活用できます。オウンドメディアに専門的で濃い情報を増やし、競合優位性を獲得していくのが望ましいでしょう。
オウンドメディアの作り方
オウンドメディアを作る場合、立ち上げ前の準備から始まり、サイト制作、運営体制の構築へと進みます。
オウンドメディアは、ユーザーが問題解決していけるように、必要な情報を過不足なく伝える必要があります。オウンドメディアの作り方について詳しく解説していくので、チェックしてみてください。
STEP1.立ち上げ前の準備
準備段階からどのようなサイトを作ればよいのかと悩んでしまい、運営方法でつまずいたり、挫折したりする人もいるのではないでしょうか。
オウンドメディアを立ち上げて成功させるためには、念入りな準備が大切です。成果を出すために、しっかり準備してから取り掛かるようにしましょう。この章では、立ち上げ前の準備について説明していきます。
目的を決める
まず、オウンドメディアを運営する目的を決めます。運営する目的が曖昧なまま見切り発車してしまうと、途中で「そもそもなぜオウンドメディアをやるのか」と疑問に思い、成果が出ないどころか、挫折につながる可能性もあります。
オウンドメディアを運営する目的には、以下のものが挙げられます。
・ 企業のブランディングへつなげる
・ 商品やサービスの購入につなげる
・ 新規リードの獲得を目指す
・ 人材の新規採用に役立てる
上記からひとつもしくは2つを選び、オウンドメディアの運営を行いましょう。
集客媒体を決める
目的を決めた後は、ターゲットをどこから集めるのか集客チャンネルを決めます。主な集客チャンネルは、検索またはSNSのどちらかに絞って決めましょう。
検索で集客をする(SEO対策)
SEOとは検索エンジン最適化を指します。GoogleなどのWebサイトで検索したときに、検索上位表示を狙う手法を言います。検索で上位表示させて多くのアクセスを集められると、オウンドメディアの目的達成に近づけるでしょう。
検索は、積み上げ型という特徴があります。検索上位を狙っている記事であれば、何年も前に作成した記事でもアクセスが取りやすいです。1記事当たりのアクセス数がほぼ変わらないと仮定した場合、記事数が増えるほどアクセス数も増えていきます。
しかし、必ずしもひとつの記事が長きにわたってアクセス数を稼げるわけではなく、短期間しか見られない記事もあるのが特徴です。
SNSで集客をしてファンを作る
もうひとつは、SNSからアクセスを集めるフロー型と呼ばれる方法です。SNSの大きな特徴と言えば、ファンを作れることです。自社のファンを増やしていくと、友達やフォロワーに対して定期的にシェアしてもらえるメリットが期待できます。
またSNSなら、潜在層と呼ばれる、検索しないユーザーにもアプローチできるでしょう。しかし、FacebookやTwitterを使うと、1か月前に投稿されたものはなかなか見られません。SNSで集客するなら、常にトレンドや旬を意識しながら投稿する必要があります。
KPIを設定する
KPI(Key Performance Indicators)とは、重要業績評価指標を指します。たとえば、資料請求やお問い合わせといったリードの獲得のために、オウンドメディアを始めるとしましょう。
その場合、月に何件のリードを獲得すればオウンドメディアの運営が順調だと言えるのか、判断する基準がKPIです。
KPIを設定しないまま運営を続けると「アクセス数が増えているから運用が順調」「アクセス数が減っているからうまくいっていない」といった曖昧な判断となってしまいます。
オウンドメディア運用の成果を正しく測るためにも、KPIの設定が重要です。
内製か外注かを選ぶ
サイトの設計と構築は、サーバー環境の準備とともに進めていく必要があります。大きく分けて、内製か外注する方法があります。
内製か外注のどちらを選ぶかは、サイトの構築のノウハウはもちろん、リソースの有無を確認して判断するとよいでしょう。
内製の場合
サイトの設計や構築を内製する場合、プログラマーやデザイナーといった技術者を雇うか、ツールを使って作るといった方法があります。それぞれのメリットとデメリットは以下のとおりです。
・ 秘術者を雇う場合:人件費が発生するが、ツールを用いるよりも高度なシステムやデザインを実現しやすい。
・ ツールを活用する場合:デザインやプログラミングの知識がなくても見た目がある程度整ったサイトを作れる。しかし、デザインの融通が効きにくい。
オウンドメディアの場合、デザインやシステムにプラスしてSEOに関する知識も重要です。自社でSEOに関するノウハウを持ち合わせていない場合は、コンサルに依頼したり、スキルのある人材を採用したりする必要があります。
外注する場合
サイト制作を外注する場合、適切な業者を選ぶ必要があります。外注する場合にはクラウドソーシングの活用や、web制作会社に依頼する方法があります。メリットとデメリットは以下をご覧ください。
・ web制作会社:オウンドメディアにおけるプログラミングやデザインはもちろん、SEOに関する対策もまとめて依頼しやすいが、コストがかかる。
・ クラウドソーシング:比較的低コストで済みやすいが、人によってレベルやスキルにばらつきがある。オウンドメディアに関するさまざまな要素をひとまとめにした依頼が難しい。イメージと異なるものを納品されるおそれや、納期が守られないリスクもある。
外注する場合、オウンドメディアに関する実績の有無はもちろん、SEOの知見についても必ずチェックしておきましょう。サイトのジャンルに関する専門知識のある人材を選ぶのが理想的です。
外注先が決まった後は、発注の仕方が重要となります。なぜなら、発注の精度が高いと、業者の提案や作業内容の質もよくなり、やり取りにかかる手間が減るからです。
サイト制作を依頼する場合、外注先に提案を依頼するための文書であるRFP(提案依頼書)を作っておくのが望ましいでしょう。サイト制作の目的やターゲット、スケジュール、課題といった情報を網羅できます。
IT業界ではRFPが扱われるケースが多いため、ネットで検索するとさまざまなテンプレートをチェックできるでしょう。
3C分析する
3C分析は事業戦略に用いられるケースが多く、オウンドメディアを構築する際に欠かせません。
3Cとは「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つを指します。3C分析を行うと、これから構築するオウンドメディアに求められる点や、成長の可能性を探れます。
Customer(市場・顧客)
最初に分析する項目です。ターゲットにする顧客を決めておくと、オウンドメディアの方針が決められます。
Competitor(競合)
競合とは、ターゲットとターゲットニーズが重なるものであり、単に同業他社のオウンドメディアとは限りません。
たとえば、操作の手軽さと機器の安さが特徴のカメラを販売する場合、ハイエンドモデルのカメラメーカーではなく、カメラ機能を備えたスマートフォンが競合となりうるでしょう。
Company(自社)
自社製品やサービスといった一般的な強みではなく、Company(自社)を分析したうえでの強みや独自性となります。
強みや弱み、新規参入の見込み、目的達成の障害になるものについて、それぞれ分析します。実施していくとメディアの方向性やルールを明確化できるため、オウンドメディアを構築する前に、しっかりと事前調査や分析を行っておきましょう。
STEP2.サイト制作・構築
サイト制作や構築は、自社で開発または外部に委託する方法があります。自社で開発する場合、サーバーやドメインを選定したりサイトデザインの選定を行ったりする必要があります。
サイト制作や構築に関する知識がない場合、成果を出せるオウンドメディアにするために、外部へ委託するとよいでしょう。
自社で開発する
オウンドメディアを自社で制作する場合、決めておく項目は以下のとおりです。
・ サーバーやドメインの選定
・ サイトデザインの選定
・ CMSの選定
オウンドメディアを立ち上げる際には、環境の整備をしておく必要があります。
・ サーバー:主流ともいえるクラウド型がおすすめ。使い勝手がよいだけではなく、機能や容量の変更がしやすい。
・ ドメイン:オウンドメディアにどのような役割を持たせるかにもよるが、新規取得より、コーポレートサイトなどのサブディレクトリ内での立ち上げがおすすめ。
外部に委託する
サイト制作や構築を外部に委託するのもひとつの手段です。成果が出やすいオウンドメディアにするためには、ユーザーが使いやすいデザインやサイト構造になっているのが重要です。
なかでも、SEOからの流入を想定している場合は、SEO対策に知見のある制作会社かどうか確認する必要があります。具体的な選び方のポイントは、以下をご覧ください。
・ 類似の業界で実績があるか
・ SEOの知見や実績
・ 料金が予算内かどうか
上記のポイントを踏まえて制作会社に依頼すると、成果につながりやすいオウンドメディアを作れるはずです。
CMSを利用する
サイトを立ち上げる環境が整った後、サイトデザインやCMSの選定を行います。CMSはコンテンツの更新や保存といった管理を手軽に行えるシステムで、代表的なものにはWordpressやHubSpotといったものがあります。
多くのCMSはサイトのテンプレートを提供しているため、希望のデザインも含めて選定するのがおすすめです。
こだわりがない場合、Wordpressを選ぶとよいでしょう。なぜなら、Wordpressはテーマが豊富なのはもちろん、ゼロからデザインを決める手間がかからないからです。
また、世界的に利用者が多いので、不明点があった場合にも解決策が見つかりやすいメリットがあります。
STEP3.運営体制の構築
オウンドメディアの構築や運営は、ひとりではこなせません。チームを作り、誰がどの仕事を担当するのか決めるのはもちろん、レギュレーションの用意、スケジュール管理を行う必要があります。運営体制の構築について、具体的にご紹介します。
運用体制を決める
仕事の流れを細かく決め、誰がどの仕事を担当するのか、一連の流れの設計をします。たとえばプロデューサーは予算管理や企画管理、クライアントとの折衝、全体の把握まで行います。
ディレクターは進行管理やクオリティ管理、末端のスケジュールを把握しておくといった体制まで決めておきましょう。
よく起こりがちなミスとして、スタッフひとりに複数の役割を任せてしまうことが挙げられます。ひとりでカバーしきれず運用がストップしてしまう事態になりかねないため、注意が必要です。
業務の流れが曖昧になってしまうと、差し戻しや修正依頼といった工程のたびに、原稿がさまざまな人の手に渡り、効率よく進みません。時間を有効に活用できるように、作業フローを決めておくのが重要です。
チームを編成する
オウンドメディアの運営は、チームで行うのが鉄則です。記事の構成や品質の管理を担う編集者、執筆を担当するライターがいなければなりません。
それだけではなく、アクセス解析やマーケティング担当、校正担当、リライト担当者がいると、質の高い記事の作成を行えます。
そしてオウンドメディアの運営を成功させるためには、高頻度での更新が必要です。そのためには人数もいなければならないため、外注ライターの募集も検討しましょう。
ディレクターやデザイナー、校正者、監修者など社外の人に依頼する場合、実績のあるフリーランスや会社に依頼してください。
マニュアルやレギュレーションを作成する
業務フローやレギュレーションは、運用しながら作成と改善を行う必要があります。レギュレーションには、ターゲットやトーン&マナー、表記統一、NGワード、引用の表記方法といった、独自ルールをまとめます。
マニュアルやレギュレーションが曖昧なまま外注のライターに依頼すると、ルールやトーン&マナーに沿った記事にならない可能性があります。内容のバラつきを抑え、なるべくイメージに近い記事を納品してもらうためにも、レギュレーションの作成は重要です。
立ち上げ時から業務フローやレギュレーションを確定するのは難しいケースもあるため、少しずつ作成しましょう。
スケジュールを管理する
編集体制が決まった後、納期やスケジュールの管理についても考えておく必要があります。コンテンツの制作が少量なら問題なくこなせても、運用期間が延びるほど、既存のコンテンツの重複といった面も考慮が必要です。
コンテンツ制作を大量にこなす場合は、進捗管理も含めて、現場に混乱が生じないように管理する必要あります。
進捗管理を各スタッフが1箇所で行えるように、情報共有の仕組みを決めておきましょう。なるべくリアルタイムで変更を共有できるように、googleスプレッドシートやクラウド型のツールを活用するのがおすすめです。
ライターへ依頼する本数とだいたいの納期を管理するだけでは、進捗に遅れが生じる可能性があります。記事ごとにライティングが完了するタイミング、校正が完了するタイミングを把握しておきましょう。
ツールを活用する
Excelやスプレッドシートの管理に限界を感じる場合、その他のツールを積極的に活用するとよいでしょう。
タスクやプロジェクト管理に利用できるJIRA、ナレッジの共有には、Confluenceと呼ばれるツールを活用します。
Confluenceなら担当ディレクターが不在でも、ほかのディレクターがナレッジボードを見れば情報共有できます。随時アクセスしてメッセージをためておけるため、ディレクター業務を柔軟に行えるでしょう。
STEP4.コンテンツ制作
コンテンツの制作を行うには、ペルソナをしっかりと決めておく必要があります。オウンドメディアのターゲットが明確でないと、方向性が定まらず、成果につながりにくいものになってしまうからです。
コンテンツ制作の順序や、ポイントについて紹介していくので、チェックしてみてください。
対策キーワードを選定する
検索キーワードとは、ユーザーが検索時に検索画面に打ち込むキーワードを指します。ユーザーの困りごとを想像し、どのようなキーワードで検索するのか、先回りして考えておく必要があります。
キーワードを決める方法は、以下から決めるとよいでしょう。
・ 検索ボリュームが多いキーワード
・ CVR(コンバージョン率)の高いキーワード
コンバージョン率とは、記事を読んだユーザーが資料請求やお問い合わせといった行動を起こす確率を指します。記事を読んでも、商品を購入したり資料請求したりする行動をしなければ意味がないため、定期的な数値分析が必要です。
ペルソナを設定する
事前調査が済んだところで、オウンドメディアのターゲットを明確にします。具体的に述べると、どのような人間なのか、属性を紐づけるペルソナの設定が必要です。ペルソナを設定する理由は、以下のとおりです。
・ ターゲットへの理解を深めるため
・ ニーズやウォンツを把握し、目標達成まで最短距離で進むため
・ 制作メンバー間でターゲットを共有するため
・ ターゲットを明確にして、制作進行をスムーズに進めるため
・ 統一感のあるオウンドメディアの構築をするため
ペルソナがぶれてしまうと、オウンドメディアの方向性が定まらず、成果につながりにくいため、適切に設定しましょう。
記事構成を作る
記事にどのような内容を盛り込めばよいか、全体の構成を作成する必要があります。キーワードをバランスよく入れたり、必要な情報を考えたりしたうえで、ライターに読みやすくなるよう書いてもらいましょう。
構成や記事作成前までに、レギュレーションを用意しておきます。長文で複雑な内容だと読み切れず、逆効果になる可能性があります。重要な点をまとめて、なるべくシンプルなレギュレーションを用意してください。
コンテンツのテーマを決めた後、記事の構成案に落とし込みます。構成案に記載する内容は、以下のとおりです。
・ 記事のタイトル
・ サブキーワード(関連キーワードやサジェストキーワード、共起後)
・ ペルソナ
・ 読み手にどのような行動をしてもらいたいか
・ 記事の説明文
・ 見出し
・ 参考資料
・ 取材先の情報
記事を作成する
キーワードや構成案が決まった後、記事の作成に入ります。SEO記事の極意は、ペルソナが問題解決できるかどうかです。
関連キーワードの調査や、上位コンテンツをチェックし、ペルソナがどのような情報が欲しいのか、問題解決を目指した記事になっているのか意識しながら作成しましょう。
記事を校正する
事実と異なる情報を掲載したり、間違った漢字を使ったりすると、ユーザーに迷惑がかかるおそれがあります。事実と異なる情報を掲載すると、もしそれが店舗に関する情報の場合、相手の業務妨害につながってしまう可能性があるでしょう。
また、正しい情報を知っている人が読むと、オウンドメディアに対してユーザーから信頼を損なってしまうリスクもあるのです。メディアに対する信頼を損ねないためにも、完成した記事の校正を必ず行いましょう。
具体的に行う作業は、以下のとおりです。
・ 誤字・脱字を確認する
・ 表記揺れをチェックする
・ 文体に統一感があるか確認する
・ 一行が長すぎないかチェックする
・ 口語表現はないか確認する
・ 冗長表現がないかチェックする
・ NGワードがないか確認する
・ 差別的な表現が使用されていないかチェックする
・ 整合性をチェックする
・ 事実と異なった内容はないか確認する
外部ライターへ依頼する場合、執筆後に自分で校正してから納品するよう、レギュレーションに校正リストを載せておくのがおすすめです。あらかじめ構成しておけば、誤字脱字や表記揺れといったエラーを減らせるため、校正者の負担軽減につながります。
STEP5.公開後のデータ分析
オウンドメディアの記事は、作成後に校正と編集をかけて公開しますが、それで終わりではありません。
定期的な分析を行って、自社のオウンドメディアでユーザーのニーズに沿ったコンテンツを提供できているか、既存記事でどれだけコンバージョン率につながっているのか明確にする必要があります。
分析をしっかりと行わないままオウンドメディアの運営をしていると、設定した目的や成果を達成できず、失敗してしまうリスクがあるからです。
オウンドメディアの成果を適宜振り返り、方向性がぶれていないか、ニーズに沿っていないコンテンツを発信していないか分析し、問題点があれば即改善していきましょう。
オウンドメディア運営で活用できる効果測定ツール
オウンドメディア運営は、高頻度で記事をアップし、効果が出ているかツールを活用して測定する必要があります。オウンドメディアの現状を把握するためにも、各ツールの特徴を把握して実際に取り入れてみましょう。
googleアナリティクス
googleアナリティクスは、Googleが提供しているアクセス解析ツールを指します。オウンドメディアへのアクセス数をリアルタイムに把握でき、期間や閲覧デバイスごとに比較も可能です。
立ち上げ時に重要となるPV数やUU数、SS数といったデータは、googleアナリティクスで分析できます。また、コンバーション数も事前に設定しておくと、googleアナリティクスで確認可能です。
googleサーチコンソール
Googleサーチコンソールは、Google検索におけるオウンドメディアのパフォーマンス解析に役立つツールです。オウンドメディアの記事の掲載順位を把握できるとされ、具体的には以下の点が分かります。
・ ユーザーが、どのような検索ワードで流入したか
・ 特定の検索ワードで、どのくらい検索結果に表示されたか
・ 検索結果に表示された回数のうち、クリック数はどのくらいだったか
Googleサーチコンソールを活用すると、SEOの観点からオウンドメディアの分析ができるため、課題把握や改善につながります。
エイチレフス
Ahrefs(エイチレフス)は、世界で利用されている有料のSEO分析ツールを指します。自社サイトはもちろん、自然検索流入キーワードや自然検索トラフィックなど確認できます。
現代はさまざまな情報であふれているため、自社のオウンドメディアを選んでもらうには、競合サイトの研究が重要です。エイチレフスは、オウンドメディア運営の成長期や成熟期に活用できるツールです。
ヒートマップツール
ヒートマップツールとは、ユーザー目線でウェブページを視覚的に表現できるツールです。サイトの訪問者はどのページを熟読して、どこからどこまでを読み、クリックしたのはどこか、ヒートマップによって可視化できます。
ヒートマップを活用すると、問い合わせや資料ダウンロードボタンの位置の調整に役立てられ、クリック率などの改善と向上を目指せます。
オウンドメディアを作る際のポイント
オウンドメディアを作る場合、ユーザーファーストを心がける必要があります。いくらSEO対策を施したとしても、見やすくて魅力的なコンテンツでなければ、ユーザーが離脱してしまうからです。オウンドメディアを作る際に心がけたいポイントについて紹介します。
ユーザーファーストを大切にする
SEO対策も重要ですが、サーチエンジンばかりを重視してコンテンツを作成しても、ユーザーが離脱してしまったら本末転倒です。
網羅性の高さや情報量の多さはもちろん、見せ方にも注意しなければ、ユーザーが読む労力を要する魅力のないコンテンツになってしまいます。
重要な箇所を強調したり、関連している写真や画像を使用したりと工夫し、独自性のあるコンテンツづくりを目指しましょう。
一貫性を持たせる
運用の目的が曖昧なままだと、コンテンツが定まらず、一貫性のない訴求になる可能性があります。一貫性を持たせるのはもちろん、ユーザーが問題解決できるコンテンツを目指しましょう。
SEO対策を施す
オウンドメディアが狙うべきSEOキーワードの選定が重要です。オウンドメディアで集客するには、SEO対策や広告、SNSといった方法があります。
SEO対策は検索ニーズが顕在化していて費用がかからず、対策しやすいメリットが期待できます。適切なキーワードを選定するなど、SEO対策をしっかりと行いましょう。
定期的に記事をリライトする
オウンドメディアは、完成した記事に校正や編集をかけ、アップして終わりではありません。成果を出していくためには、継続的な記事作成はもちろん、既存記事のリライトが重要です。
サイトの規模やかけられる予算を考慮しながら、外部へ依頼するかどうかなど、運用体制も決めていきましょう。
成果が出るまで時間がかかる
オウンドメディアの運営は、成果が出るまでに時間がかかると理解しておきましょう。とくにSEOコンテンツは公開してすぐに評価されるわけではなく、立ち上げ当初は評価されるまでに時間がかかる傾向があります。
定期的に記事を更新していくと検索エンジンに評価され、アクセス数が増えて、ユーザーとの接点が生まれるといった段階を踏みます。
SEO対策は、短距離走ではなく長距離走です。成果の測定には半年から1年はかかるため、忍耐強く継続する必要があります。
オウンドメディアの構築や運用にかかる費用
オウンドメディアを構築する場合、サーバーやドメインにかかる費用のほかに、サイト制作や分析ツールにも費用がかかります。
サイト制作を内製するか外注するかによっても費用が大きく異なるため、余裕をもって予算を確保する必要があります。オウンドメディア構築や運用にかかる費用を見ていきましょう。
サーバー費用
レンタルサーバーまたはクラウドサーバーを活用する場合、5,000~100,000円の年間費用が発生します。サービスやサイトの段階によって、大幅に金額が変わります。
メディアが大きくなってデータやアクセスが多くなれば、その分費用も高くなります。また、クラウドサーバーはレンタルサーバーよりも性能が優れているため、料金が高い傾向があります。
ドメイン費用
オウンドメディアの作成にともなって、独自ドメインを新しく取得する場合、1,000~3,000円ほど年間費用が発生します。ドメインの種類によって料金が異なるのが特徴です。
たとえば末尾が「.com」や「.net」になっているドメインは、誰でも取得でき、比較的安い傾向にあります。一方「.jp」が末尾になっているドメインは、日本でしか取得できないため料金が高額です。
サイト制作費用
サイト制作を内製する場合、採用コストや人件費だけで済みます。しかし、内製ではなく外注するなら、数十万万円~数百万円ほどコストが発生するため注意が必要です。
たとえばサイトデザインにこだわりがなく、記事投稿の準備さえ整えばよいという場合は数万円で済みます。一方、戦略の策定や計画立案までサポートしてもらいたい場合、数百円以上のコストがかかると考えておきましょう。
記事制作・外注費用
記事制作にかかる費用は、ライターの文字単価や記事のボリュームによって変動するのも覚えておきたいポイントです。
たとえば、依頼したい記事の分野について、深い知識を持っていたり資格を有していたりするライターに依頼する場合、文字単価も上がる傾向にあります。
分析ツール費用
分析ツールの費用は、オウンドメディアの段階によって変動します。立ち上げ期であれば無料で済ませられますが、規模が大きくなってくれば、最大で年間 で数百万円ほどかかるケースもあるでしょう。
各費用は参考額となり、ご依頼内容によって変動致します。
まとめ
オウンドメディアの記事は、誰が読んでも理解できる文章を心がける必要があります。チームを編成し、念入りに準備をしながら進めていくことが重要です。
オウンドメディア運営は、定期的に記事をアップし、効果が出ているかツールを活用して測定します。改善が必要な場合は、記事をリライトしたり対策を講じたりしながら、運営しなければなりません。
株式会社PA Communicationは、オウンドメディアの開発、記事制作、SNSと連動しながらECサイトを改善し、購買促進からファン化まで、戦略的かつ包括的なサポートを行っています。
オウンドメディア作りや集客方法で不明点のある方は、せひお問い合わせください。
▼弊社オウンドメディアの事例はこちら
■Vibrram
日本限定のオウンドコンテンツ「Vibram-ism」の立ち上げをサポート
■資生堂プロフェッショナル
サイトトラフィック最大化に向けた支援 /資生堂プロフェッショナル
■ルミアグラス
認知拡大のためのデジタル施策!アイライナーブランド「ルミアグラス」のオウンドコンテンツの制作
****************************************
PACでは、お客様の課題に合わせて最適なサービスを提供しております!
お気軽にご相談ください。
コンテンツプロデュースについて
デジタル戦略について
お問い合わせ